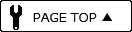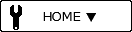第2種電気工事士合格.com
 第2種電気工事士技能試験、公表問題配線図 NO.2
第2種電気工事士技能試験、公表問題配線図 NO.2
技能試験で、出題される配線図を公表問題として、13種類の配線図が用意されます。
実際の技能試験では、公表された配線図のうち、ランダムに選ばれた配線図の電気配線加工を行います。公表された配線図と、試験の配線図はケーブル長や使う器具等、微妙に異なる配線図が使われますが、大きく異なることはないので、事前に公表された配線図を使い、何度も練習することが、技能試験合格の近道となっています。
埋込スイッチを使ったもっともオーソドックスな課題は、13の課題のうち、4問ほどあります。1問でも覚えれば、後の3問は似た問題なので覚えなくても問題ありません。
スポンサード リンク
 公表問題NO.2 スイッチ系
公表問題NO.2 スイッチ系
コンセントとスイッチ部分が少しややこしいですが、比較的、オーソドックスなスイッチ系の配線図となっています。
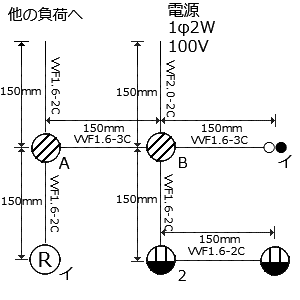
- ◆施工特記事項
- Aのジョイントボックスでは、差込形コネクタを使った接続
- Bのジョイントボックスでは、リングスリーブを使った接続
施工省略部と電源線の端末処理は、VVFケーブルを切りっぱなしで構いません。
 公表問題NO.2 複線図
公表問題NO.2 複線図
技能試験の配線図は、初見で線の色や数が分からないので、実際に作業しやすいように、複線図と呼ばれる、実際の配線に近い図を書いた方が分かりやすいです。
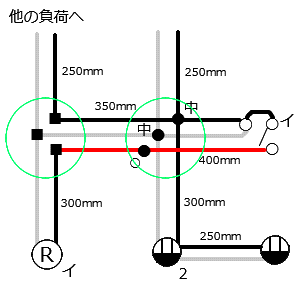
複線図には、実際に切断するケーブル長、リングスリーブの圧着マーク、線の色を記入するのが基本です。
NO.2の公表問題では、あまり複雑な配線はないので、細かな注釈まで記入すると、余計に混乱する可能性もあるので注意して下さい。
試験では、色ペンを持参しても問題ないので、赤や青など、自分なりに分かりやすい色を使うことができます。
 公表問題NO.2 難解ポイント
公表問題NO.2 難解ポイント
この問題のポイントは、2つのコンセント間のケーブルの寸法切りです。コンセント間が150mmと配線図で示されていますが、シース部分は100m、左右共に絶縁被覆部分は75mmで配線します。
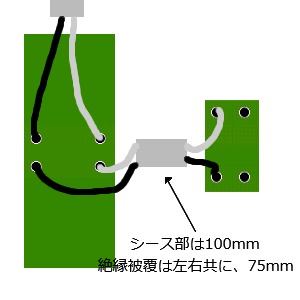
他のポイントとして、リングスリーブの刻印も間違いやすいので注意して下さい。1.6mm×4本までは小の刻印ですが、この問題では、2.0mmのケーブルがる箇所が4本配線となっているため、中刻印でないと失格となってしまいます。
1.6mmが2本の時は、圧着マークは○。8mm2以下の時は小。9mm2以上13mm2以下の時は中。
1.6mm=2mm2。2.0mm=3.5mm2。
 公表問題NO.2 練習手順
公表問題NO.2 練習手順
私自身がタイム測定し、公表問題NO.2を完成させるまでの手順を紹介します。ちなみに練習タイムは、22分00秒でした。

私が練習で仕上げた完成品です。かなりきれいに仕上がっていますが、結線部分のケーブルを少し上側に折り曲げると、ケーブルが整えやすいです。
電源ケーブルは、本来青いケーブルですが、間違えて、灰色のケーブルを使ってしまっていますが、ご愛敬ということで。電源ケーブルから作りはじめ、シース部分をむき、絶縁被膜も剥くところまで仕上げます。人により手順は様々ですが、一度すべてのケーブルの寸法をカットしていくよりも、1本1本仕上げていく方が時間はかかりますが、結線忘れや、ケーブルの寸法ミス等の失敗は少ないと思います。
ランプレセプタクルの部分、施工省略部分のケーブル、真ん中のケーブル、コンセントの部分、最後にスイッチ部分に取りかかります。
コンセントの部分は、わたり線も含めて、黒と白の結線だけなので、とても簡単に仕上がります。1個口のコンセントの部分の絶縁被覆は、50mmで剥いています。埋込み型枠を付けない、コンセントやスイッチ部分の絶縁被覆は、100mm剥くと長すぎるので注意して下さい。見栄えが悪くなります。
最後に、リングスリーブ、差込型コネクタの結線を行います。差込型コネクタは失敗して結線をしても簡単にやり直しができるので、差込型コネクタの結線から行います。
リングスリーブは、刻印を間違えないように、電源ケーブルの白(接地側)から、かしめていきます。白(接地側)は、器具とコンセントに結線します。
見直し、見栄えを整えても、十分な残り時間があると、もしものミスの時にフォローがしやすいので、なるべく残り時間が多くなるように素早い作業も大事になってきます。
スポンサード リンク